- そもそもDX(デジタルトランスフォーメーション)とは何なのか
- DX化の事例
- 日本でのDX化の現状
- DX化の進め方
DX(デジタルトランスフォーメーション)という単語を聞くことが増えてきました。しかし、アルファベットでDXと聞いても良く分からないと思う人もいるはずです。
とにかく、DXという言葉の意味とイメージを掴みたいという人は目次1の内容を読むだけで理解できるようになっています。
- DXに興味がある人
- 会社でDXが推進されている人
- ITの学習をしている人
そもそもDXとは【定義・意味・事例・いつから】

DXの意味について、経済産業省が次のように定義しています。
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」
経済産業省:デジタルガバナンス・コード2.0
分かりやすく言うと、「最近はIT(情報技術)の発展スピードがすごいし、めっちゃ便利になってきてるから、もっとビジネスにITを取り入れて、会社を発展させよう!」ってことです。
日本では、2018年に経済産業省が「デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」を発表したことで、DXという言葉が広く認知されるようになりました。
日本で使われるDXの意味とは、経済産業省が定義したものになります。
じゃぁ、DXっていつどこで生まれたの?という疑問もありますよね。
2004年に、スウェーデンのウメオ大学教授である、エリック・ストルターマンさんがデジタルトランスフォーメーション(DX)という言葉を作りました。
もともとの意味については、総務省がまとめている情報通信白書令和元年版が紹介しています。
ICTの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること
総務省:情報通信白書令和元年版 第1部 第1節 デジタル経済の特質は何か
ICT(Information and Communication Technology)とは、情報通信技術のことです。ITとICTって似てるけど何が違うんだ?と思われたと思います。
2つの違いは、ICTの方が情報の伝達を重視しているという点です。それくらいの違いしかないので、ほぼ同じ意味の言葉と思って頂いて大丈夫です。
DX化の事例については、経済産業省が「DX Selection 2023」という資料がまとめています。
DXセレクション(中堅・中小企業等のDX優良事例選定)とは、令和3年度から経済産業省が始めたもので、中堅・中小企業等のモデルケースとなるようなDX化優良事例を選定したものです。
気になる方はご覧ください。
詳細はこちらから経済産業省「DX Selection 2023」
ここまでで、DXとは何かというイメージが大体理解できたのではないでしょうか。
続いては、「DX Selection 2023」を読んでみたけど、よく分からないという人の為に事例などを分かりやすく解説し、少し深堀していきます。
中小企業のDX化の具体的な事例・成功例の紹介

先ほど紹介した「DX Selection 2023」でグランプリを受賞した「株式会社フジワラテクノアート」のDX化事例を紹介していきます。
株式会社フジワラテクノアートは、味噌や醤油等の醸造食品を製造するための機械を開発しているメーカーです。
まず「DX Selection 2023」の、「DXによって実現したい経営ビジョン・ビジネスモデル」と「DXを進めたことによる具体的な変化」の項を確認してみましょう。
内容は以下の通りです。
少し難しいかもしれないので、下に要点をまとめています。
DXによって実現したい経営ビジョン・ビジネスモデル
- 「醸造を原点に、世界で『微生物インダストリー』を共創する企業」として、「微生物のチカラを高度に利用するものづくり」を様々なパートナーと共創し、心豊かな循環型社会に貢献する。
DXを進めたことによる具体的な変化
- 3年間で21システム・ツールを導入して全工程が進化し、ビジョン実現に向けた新たな価値創造のための業務により時間を費やせるようになった。
- 社員が未来志向となり、DX推進委員以外の社員からも意見が出るなどDXが加速した。またデジタル人材増加により、スピーディにDXを推進できる体制となり、DXの内製化に成功した。
- 主要協力会社との取引をオンライン化し、各社のDX推進の契機となった。また協力会社を巻き込んで情報セキュリティ対策を進めた。
参考:経済産業省 DX Selection 2023 DXを進めたことによる具体的な変化 4P
DXを進めたことによる具体的な変化が、つまり成果と言えます。簡単な言葉にして以下にまとめてみます。
- システムを導入したことで、作業が効率化したから、ビジョン実現のための時間を作ることができた
- デジタル人材が増加して、DXを自社で行えるようになった
- 取引先とのやりとりもオンライン化したことで、自社だけではなく取引先の仕事も効率化した
ここで特に大事なことは、「ビジョン実現のための時間を作ることができた」という点です。
DX化やシステム導入の成功条件は、最初に定めた目的を達成すること
株式会社フジワラテクノアートは、経営ビジョンで「共創」という言葉を2回使用しています。そして成果として「ビジョン実現のための時間を作ることができた」と言っていることから、「共創」のためには「時間の余裕が必要」と考えていたことが分かります。
当初の目的を達成していることから、このDX化は成功した事例と言えます。
株式会社フジワラテクノアートが、今回のDX化についてまとめた資料を公開しているので、興味のある方は参照してください。
「フジワラテクノアートの DX 推進について」
日本企業のDX化の現状・推進状況

事例は分かったけど、じゃぁどのくらいの企業がDX化を推進してるの?と疑問に思いますよね。
経済産業省の機関である、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発行している「DX白書2023」を参考に見ていきましょう。
ちなみにIPAとは、国家資格である、「ITパスポート試験」や「基本情報技術者試験」を実施している機関です。
企業のDX取り組み状況
- 大企業で4割強
- 中小企業で1割強
この数字を見てどう思いましたか?少ないと感じたでしょうか。
私は、かなり多いと感じました。
というのも、日本の中小企業は300万社、400万社あると言われています。
設立だけしてあり、実働していない会社もあると考慮し、中小企業の数が200万社と仮定しても、20万社以上の中小企業がDXに取り組んでいることになります。
大企業は、1万社程度と言われているので、4000社しかDXに取り組んでいないことになります。
日本の中小企業凄すぎる…
企業がDXに取り組むための課題
- 資金不足
- 費用対効果が分からない
- IT人材不足
確かに、システムの導入などはかなり高額になります。DX化の事例の紹介で挙げた「株式会社フジワラテクノアート」の事例では、「3年間で21システム・ツールを導入して全工程が進化」とありました。
恐らく、この規模でシステムを導入したとすると、1億円以上掛かっていると思います。
全工程が進化したと書いてあるので、資金を回収できる計画ではあると思いますが、そもそも規模の小さい会社だと、その資金をどうやって調達するという話になります。
IT人材についても、わざわざITに詳しい人はIT企業に行くので、業種の違う中小企業には就職しませんよね。
課題が分かったところで、じゃあ中小企業はどうすればいいの?と思われているはずなので、対策について紹介します。
資金がない中小企業がDXに取り組むための方法
- 社員のITスキル向上
- IT導入補助金の利用
基本的に取れる手段はこの2つです。
社員のITスキル向上
資金を出したくない場合
自発的に社員に学習してもらうことしかできず、本格的なDX化は難しいと言えます。少しずつでもいいので教育を行い、ITスキルを身に着けることで良いアイデアが生まれるかもしれません。
また、例えば社員にExcelのVBAを学んでもらうと業務の効率化を図れるかもしれません。
ほとんどの会社ではExcelを使用していると思いますが、Excelをより使いこなすことができれば、多くのことで役に立つはずです。
社内フォルダを整理したい場合を想定したExcelの使う方をまとめている記事があるので良ければ参照してみて下さい。
資金を出すつもりはあるが節約したい場合
システムを導入することが前提であるならば、IPAの資格である「プロジェクトマネージャー」や「応用情報技術者」の資格を取得してもらい、RFP(提案依頼書)の作成方法を学んでもらうことで予算の削減を図れます。
ただし、社員のモチベーションが重要なので、合格したら報奨金を用意するなど対策が必要です。
なぜこれが予算の削減を図れるのかというと、システムを導入する際はIT企業にRFP(提案依頼書)の作成を依頼することが多いです。このRFP(提案依頼書)とは、システム開発会社に提出するもので、こんなシステムが欲しいといった内容が書かれたものです。しかも結構お高く、数百万円したりします。
数百万円払うより、社員に報奨金を出した方が良いですよね。
このRFP(提案依頼書)をほぼ自分たちで作り、アドバイザーをどこかのIT企業に頼むことが出来れば、かなり安くなると思います。
資格を取得しても、実務経験がないと理解できないことも多々あると思うので、アドバイザーはどこかに依頼した方が無難です。
また、システム導入となると社員の拘束時間が結構生じます。その時に、資格を持っている社員がいれば物事をスムーズに運ぶことができ、余分に発生する時間的コストを削減することができるでしょう。
IT導入補助金の利用
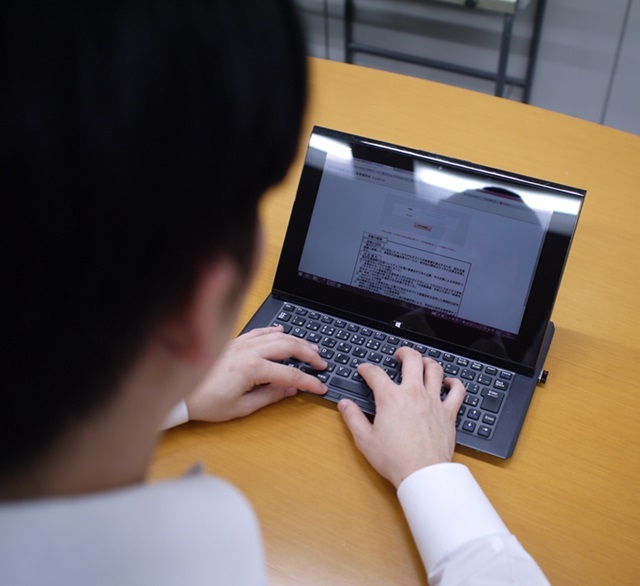
国の制度でITに関する補助金を出してくれるものがあります。
結構利用している中小企業があるのでおすすめです。
詳しくは、国の公式のホームページに全て書かれているのでリンクを貼っておきます。
DX化の進め方を簡単に解説

普通に説明しようとするとかなり長くなるため、重要なポイントについて簡単に解説します。
DX化の事例の紹介でも書きましたが、DX化やシステム導入の成功条件は、最初に定めた目的を達成することです。その目的とは、経営ビジョンの達成です。その経営ビジョンの課題となっていることを整理する必要があります。
- 経営ビジョンの再確認
- 経営ビジョンを達成するに当たっての課題の整理
経営ビジョンを意識する理由としては、全社一丸となる必要があるからです。そのため、最初の段階から社長や経営層が参加する必要があります。
そして、「一番最初に行うこと」をする際は、プロジェクトチームを作って下さい。
誰が責任者か担当者か明確にしましょう。責任者は経営層にしてください。
システム業者の候補を見つけましょう。
そして、課題が浮き出てきたら、「システム導入スケジュール」を作成してください。
このスケジュールに沿って、システム導入プロジェクトは進行します。
簡単ではありますが、プロジェクトの実行計画書のサンプルを載せている記事があるので、よければ参考にしてください。
さいごに
DXについて理解は深まったでしょうか。会社として本格的にDXをしない場合でも一人一人がITについて学習すれば、業務の効率化を図ることも可能です。
もし少しでも興味があれば、プログラミングの学習をすることもおすすめします。







